
コールセンターとは

コールセンターとは、顧客との電話対応専門部門です。
コールセンター業務は「インバウンド業務」「アウトバウンド業務」「フルフィルメント業務」の3つに大別されます。
インバウンド業務
顧客や取引先からの受電対応業務です。
顧客からのお問い合わせや取引先からの受注など、さまざまな内容に柔軟な対応をする必要から、一定レベルのスキルが求められます。
具体的な業務内容は以下の通りです。
- 業務外時間などの一次対応
- 商品の注文
- 予約受付
- 商品やサービスに関する問い合わせ
- クレーム処理
アウトバウンド業務
自社から顧客や見込み客に架電する業務です。
いわゆる「テレアポ」をイメージすればいいでしょう。
一般的にはマニュアルに従い、電話をかけていきます。
新規顧客獲得の場合は相当数のリストにアプローチする必要があります。
具体的な業務内容は以下の通りです。
- 新規顧客獲得(テレフォンアポイント)
- マーケティングリサーチ(テレマーケティング)
- 商品購入やキャンペーン申し込みなどのお礼
- 新規サービスや商品のご案内
- セミナーのご案内
フルフィルメント業務
近年増加しているニーズで、ECサイトを運営する上で必要な一部の裏方業務に対応します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
- 顧客からのお問い合わせ対応
- リピーターへのアフターフォロー
- メール・チャット返信対応
- 商品の発送手配
- 在庫状況確認
具体的な仕事内容
コールセンターが取り扱う商品・サービスは多様なので、様々な業務に対応します。
| 業種 | 内容 |
| テレフォンオペレーター | 商品の注文や問い合わせ・サービス加入などへの対応・取次ぎを行います。主には新規顧客が中心 |
| カスタマーサポート | 商品やサービスに関する問い合わせ・対応を行います。主には既存顧客が中心 |
| テクニカルサポート | 操作方法や解決方法など、技術的な問い合わせに対応。冷静な判断力・ヒアリング力が求められる |
| テレフォンアポインター | 通称「テレアポ」。顧客リスト等を元にして自社の商品やサービスを紹介します。忍耐力が求められやすい |
| テレマーケティング | マーケティングなど、商品やサービスの市場調査や満足度調査を目的とする。既存顧客が中心 |
取り扱う商品・サービス
仕事内容や取り扱う商品も様々です。
コールセンターの仕事内容の一例を挙げてみます。
| 業種 | 業界と内容 |
| テレフォンオペレーター | 通販会社・家電メーカー・健康食品・化粧品など |
| カスタマーサポート | カード会社・保険会社・通信会社・イベント会社など |
| テクニカルサポート | 家電メーカー・PC修理・インターネット・故障・通信接続・システムトラブル・操作方法の案内等 |
| テレフォンアポインター | 保険セールス・融資・マンション販売・料金督促・求人広告・家庭教師・太陽光発電など |
| テレマーケティング | マーケティング調査・世論調査・アンケート調査・満足度調査・フォローコールなど |
コールセンターのメリット

コールセンターの活用メリットは「コスト」「品質」「時間」「本業への集中」など。
自社でコールセンターを用意するには相当なリソースが必要なので、大企業でなければ現実的な選択肢になり得ないでしょう。
資本力のある企業以外は、外注化が正しい選択だと思われます。
コスト
コールセンターを自社構築する場合、コールセンターの設置費用などの初期コストと人件費、システム整備費などの運用コストが発生します。
一方、外注はすでに整備されたインフラを使用できるので、莫大な初期コストは必要ありません。
また、コールセンター代行会社の多くは、オペレーターの席数や問い合わせ数に応じた従量課金型の料金体系を採用しているため、無駄な運用コストも発生しにくくなっています。
品質
コールセンター代行会社は、実務経験の中から豊富なノウハウを蓄積しているため、クレーム対応などの難易度の高い業務も無難に消化してくれます。
オペレーターの教育システムも確立しているため、人材の補充も容易です。
また、マニュアルや業務フローを実務の中で改善を重ね、より高いレベルに磨き上げていくスキルもあります。
このようなコールセンター代行会社の高度なノウハウを活用することができるのです。
期間
コールセンター運用までの手順は以下の通りです。
1. 顧客満足度などの現状分析
2. KGI(重要目標達成指標)と、そこまでの中間目標の設定
3. 必要な設備規模やオペレーター数の調査
4. 組織体制、業務のプロセス、管理体制の計画
5. マニュアルの作成
6. 回線やツールの導入
7. オペレーターの採用、育成
8. 稼働
このプロセスを社内で実現するには相応の時間がかかりますが、外注であれば短期間での稼働が可能になります。
場合によっては即日対応も可能も不可能ではありません。
本業への集中
コールセンター代行会社への外注化で、顧客対応に割いていた社内人材を他の業務へ振り向けることができ、本業への選択と集中が実現できます。
予算や人材などのリソースが限定される中、顧客対応などの仕事を減らして、より重要度の高い業務に集中することが可能になるのです。
コールセンターのデメリット

ノウハウの蓄積
コールセンター代行会社のノウハウ借用は、自社内でのノウハウ蓄積ができないことと同義になります。
コールセンターの外注は、期間限定のプロジェクトや事業規模拡大を期さない業務の場合などに特に有効と考えられます。
セキュリティリスク
委託内容によっては、顧客の個人情報や企業情報をコールセンター代行会社と共有することになります。
コールセンター代行会社のセキュリティ対策に問題があった場合、大事故に発展するリスクがあります。
コールセンターを外注する際は、厳重なセキュリティ体制を敷いている会社であることが必須条件になります。
また、情報漏洩時の補償などもチェックしておきます。
コールセンター代行会社の選び方

コールセンターの外注は、決して安価ではありません。
そのため、会社選びを失敗すると「顧客満足度の低下」「リソース・資金の無駄」などを覚悟しなければいけなくなります。
外注化に必要なポイントを理解し、自社に最適なコールセンター代行会社を選定しましょう。
費用対効果
コールセンター外注化での最重要事項は「費用対効果の最大化」です。
そのために、まずはサービスの要・不要を明確にします。
外注化でしか解決できない課題が明確になれば、最低限必要な機能が理解できるはずです。
ポイントは「価格ではなく、機能との見合い」です。
つまり費用対効果です。
価格を最優先にしてしまうと、必要機能の欠如や品質が低下するリスクがあります。
パー・コール契約
パー・コール契約とは、架電した件数に応じた料金を支払う形態で、アウトバウンド業務に適した契約形態です。
アウトバウンド業務は決められたリストにコールするので、時間や人員のコントロールが可能になるため、パー・コール契約が採用できるのです。
パー・ブース契約
パー・ブース契約は、主にインバウンド業務に適した契約形態です。
インバウンド業務は顧客や取引先からの連絡が不定期で読めないため、常に人員を配置しておく必要があります。
そこで、人員数と時間に応じて金額が変動するパー・ブース契約が採用されるのです。
また、インバウンド業務を委託する際の費用は、電話の一次受け対応、メールやチャットを使用した対応、データ入力、受注や予約の受付、顧客からのクレーム対応、トラブルや不具合への緊急対応、技術的な問い合わせに関するサポート対応、取引先からのお問い合わせ対応、対応時間・曜日 などの要件によって異なります。
対応可能時間
コールセンターは24時間対応を求められることがあります。
通常の営業時間が終了した深夜帯などに問い合わせが発生する場合を考えて、外注先を選ばなければなりません。
コールセンター代行会社によっては、24時間対応や休日対応などのオプションを提供しているので、選定の際は必ず確認しておきます。
電話以外の対応
コールセンター代行会社選びでは、マルチチャネル対応がポイントのひとつです。
近年は、SNS、チャット、電子メール、Webサイトなど、多チャネルでの対応が求められます。
業種
コールセンター代行会社には得意・不得意な業種があります。
また、業種によっては深い専門性が求められる場合があります。
特殊な業界では必要な前提知識が多く、オペレーターにも高度な理解が求められますが、それは教育コストの高騰を意味するので、外注化の実現が困難になるかもしれません。
サービス品質
顧客対応では、顧客満足度の向上が最重要テーマですが、オペレーターの教育によって対応の良し悪しが大きく左右されます。
オペレーターは入れ替わりが激しく、サービスの質を維持するのが難しい業務です。
コールセンター代行会社の選択時には、人材育成に注力しているが大きなポイントになります。
人件費削減のために少人数で運用している会社は、就業環境が劣悪になりがちなので注意が必要です。
コールセンター委託の手順
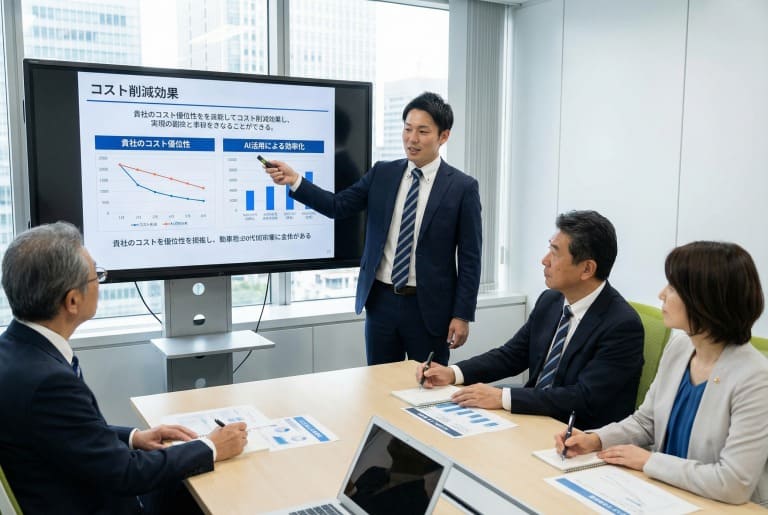
コールセンター業務は、以下のような流れで委託し運用していきます。
見積・契約
コールセンター代行会社を選定し、要件を伝え、見積もりをもらいます。
内容に合意できれば契約を締結し、サービス開始日を決定します。
業務設計
コールセンター業務の設計および構築をします。
ここで認識の齟齬が発生しないように、丁寧なコミュニケーションを実施します。
運用テスト
コールセンター代行会社が、必要書類の作成をし、オペレーターの教育研修を実施します。
その上で運用テストを行い、業務内容の最終確認をします。
運用開始
業務設計や運用テストに問題がないと確認できれば、実際の運用を開始します。
失敗しないコールセンター選びのポイント

コールセンター外注後に後悔することがないよう、以下の点を確認します。
コールセンター外注のゴールを明確にする
コールセンター外注の目的や目標を明確にしておきます。
コールセンター代行会社は、規模やサービス内容、得意分野などが異なります。
会社選定の前段階で、依頼する目的と得たい成果(ゴール)を明確にし、求める要件・会社選びの指標に落とし込んでおきます。
ゴールを明確にできていれば、その分野に強みを持つコールセンター会社をスムーズに絞り込んでいくことができます。
依頼内容を明確にしておく
依頼内容をある程度明確にしておくことも大切です。
コールセンターの構築過程では、多くのことを決定し、さまざまなプロセスを経る必要がありため、依頼内容が明確になっていないとトラブルを誘発することになります。
具体的には、コールセンター運営の目的と目標、インバウンドとアウトバウンドのどちらが希望か、インハウス(内製)とアウトソース(外注)のどちらが希望か、依頼期間、取扱商材と顧客層、業務詳細(席数などのボリューム、営業時間)などを検討しておくと失敗を防ぐことができるでしょう。
条件
外注業務に必要な要件や予算など、自社が必要としているコールセンター業務を予め整理すると、スムーズな業務進行が可能になります。
提案の確認
コールセンター代行会社からの提案内容を確認します。
会社によって得意分野や専門分野が異なるので、提案内容を精査しておきます。
セキュリティレベル
コールセンター代行会社に社内情報や顧客情報を渡す場合、情報漏洩のリスクが発生します。
プライバシーマークやISO27001を取得しているかなど、セキュリティレベルの確認が必須になります。
スタッフの教育
オペレーターを含むスタッフに対する教育やトレーニングの実施状況を確認します。
顧客対応をするオペレーターの質により、自社のブランド価値が大きく変化します。
自社名での顧客対応を任せてもよいかを慎重に判断します。





