
日本標準産業分類における「農業・林業」は、自然資源を活用し、米、野菜、畜産などの食料生産や木材などの林業生産を行う重要なセクターで、一般的には第1次産業と呼ばれています。
農業がなければ食卓に食べ物が並ばず、林業がなければ木造住宅は建ちません。
それでは生活が成り立たなくなるでしょう。
生きるために不可欠な産業である農業・林業の特徴や代表的な企業について詳しく解説します。
農業・林業の定義と分類

農業は、農地を利用して作物の栽培や家畜の飼育を行う産業で、食料生産を主たる目的としています。
林業は、山林での樹木の育成・伐採・加工を中心に、木材やその他の林産物の生産を主眼にしています。
日本の産業分類において第1次産業に位置付けられ、いずれも生活に欠かせない基礎的な生産活動を行っています。
米の生産は太古の昔からあり、日本人の生活に密着しているだけでなく、国の経済や文化に深く根付いた分野といえます。
農業・林業の規模

農業・林業の規模は以下の通りです。
農業・林業の規模は製造業などに比べれば決して大きくありませんが、食料・資源の安定供給や環境保全、そして地方での雇用確保など、国や地域社会にとって不可欠な役割を果たしています。
経済規模
農業・林業のGDP(国内総生産)に占める割合は、他の産業に比べ、決して大きくはありません。
具体的に日本の農業・林業はGDPの1~2%程度を占めるに過ぎません。
農業は国内の食料供給を支えていますが、製造業やサービス業に比べて経済規模が小さく、林業は国策としての資源活用が進む一方で、輸入木材との競争や後継者不足により国内生産が縮小傾向にあります。
就業人口
農業・林業の労働人口は減少傾向にあり、農業従事者は総就業人口の約3.4%程度、林業従事者はさらに少数です。
また、高齢の進展による後継者不足が大きな課題ですが、労働力不足を補うために外国人技能実習生やロボット技術の導入が国策として進んでいます。
面積
都市化や人口減少、さらに後継者不足などが要因で農地面積は約440万ヘクタールとピーク時に比べて大幅に縮小しています。
林業については、国土の約66%が森林であるため、木材供給の面では心配ありませんが、担い手不足から保守されていない山林も多く、環境保全の観点からは懸念が持たれます。
生産規模
日本の農業は稲作や果樹栽培が中心で、食料自給率は決して高くなく、輸入食品の割合が高くなる傾向が続いています。
食料自給率はカロリーベースで37%です。
林業の国内木材自給率は30~40%程度ですが、森林環境税の徴収が始まるなど、国産材の需要拡大に向けた取り組みが進められています。
収益性
農業・林業は、農産物加工や販売、観光農園の運営などを通じ、第1次産業✕第2次産業✕第3次産業=6次産業化を実現させ、収益性を向上させています。
また、道の駅の整備などにより、農家による直接販売が可能になり、収益性が向上しています。
また、ICT技術やAIによるスマート農業の導入で、大幅な効率化と規模の拡大が期待されています。
農業の特徴

多様な作物の生産
日本の農業は、米、麦、大豆、野菜、果物、花卉など、多種多様な作物の生産が特徴で、その上高品質で美味しいため、近年では海外にまで販路を広げています。
各地域の気候や地形に応じて品種改良がなされ、特産品が生産されており、地域経済や文化の発展に貢献しています。
季節労働と収入変動
一昔前ほどではないにせよ、それでも農業は季節によって作業内容が大きく変動し、繁忙期と閑散期が明確になる傾向にあります。
また、天候や市場価格の影響を受けやすく、収入の不安定化が懸念されるため、若者が敬遠する一因となっています。
リスク分散として林業などとの兼業やネットとの融合を目指すケースも見られます。
技術革新と効率化
近年、ICT(情報通信技術)やAIを活用したスマート農業が注目され、生産効率の向上や労働負荷の軽減が進められています。
ドローンの活用やGPSを活用した自動運転のトラクター、カメラとロボットによる収穫など、人的労働力に頼った産業からの脱皮を急ぎ、収益性も向上させようとしています。
これにより、若者の就労意欲向上や異業種からの参入も増加しており、少子化が進む日本において、明るい未来が示唆されています。
林業の特徴

長期的視点での資源管理
林業は、樹木の成長に数十年を要するため、長期的な視点での資源管理が求められる、根気を要する産業です。
適切な間伐や植林を行い、森林の健康を維持しながら持続可能な木材生産を目指しますが、相応な人的資源の投入が欠かせません。
多様な製品と用途
生産される木材は、建築資材、家具、紙製品など、さまざまな用途に利用されます。
また、薪や木炭、樹脂、樹皮などの副産物も重要な資源として活用されています。
外食時に使用する割り箸も、この木材資源から製造されています。
労働環境と機械化
山間部での作業が多く、労働環境は総じて厳しいですが、近年では高性能林業機械の導入やICT技術の活用により、作業の効率化と安全性の向上が図られており、後継者不足解消の一助になると期待されています。
農業・林業の相乗効果

繁忙期の違い
特に山間部においては、農業と林業では繁忙期が異なるため、両方を兼業し、年間を通じて労働力を有効活用する事例も散見されます。
労働の平準化を通じて、効率的に労働力を活用でき、収入増加にも貢献できる取り組みです。
収入の安定化
農業は天候や市場価格の変動に影響されやすく不安定さが払拭できませんが、林業との兼業で収入源を多様化し、経済的な安定を図れます。
技術と知識の活用
農業と林業の技術や知識を相互に活用し、生産性の向上や環境保全に寄与する取り組みが盛んになっています。
農業の土壌管理技術を林業に応用できれば、森林の健康維持が可能になるなど、WIN:WINの関係が期待できます。
代表的な農業・林業の企業

農業分野の有名・注目企業
カネコ種苗株式会社
種苗最大手企業です。野菜 · 飼料・緑肥作物 · 景観作物・芝 · 培土 · 肥料 · 養液栽培・温室 · 生産用花きなど、幅広い種苗を提供しています。

カネコ種苗株式会社
1.野菜・飼料作物・花の種子の育種・バイテク研究 2.植物工場、養液栽培プラントの開発 3.種子生産 4.温室建築、造園工事設計・施工 5.種苗・花き・農薬・施設園芸用諸資材卸売
株式会社サカタのタネ
国内最大手種苗メーカーで、花・野菜・ハーブ・農園芸資材の豊富な種を農家から愛好家の方まで、幅広く提供しています。

株式会社サカタのタネ
種苗卸売業
株式会社雪国まいたけ
まいたけ・えりんぎ・ぶなしめじなどを小売する、きのこ販売の大手企業です。

株式会社雪国まいたけ
まいたけ、えりんぎ、ぶなしめじ等の生産販売及びきのこの加工食品の製造販売
ホクト株式会社
雪国まいたけと並ぶ、きのこ販売大手で、テレビCMでもお馴染みです。

ホクト株式会社
きのこの生産・販売
株式会社アクシーズ
食の源流を自らの手で磨き上げるように、原料から製品まで一貫して品質哲学を貫く企業です。単なる加工ではなく“命の循環”を見つめる姿勢で、安全性と風味の精度を高め続けています。

株式会社アクシーズ
鶏肉及びその加工食品の製造販売
株式会社ホーブ
農産物を単なる食品ではなく“時間と環境の結晶”として捉え、その価値を独創的な加工技術で磨き上げる企業で、自然が育む味わいに精緻な職人性を重ね、地域の恵みを新たな食文化へ昇華させます。
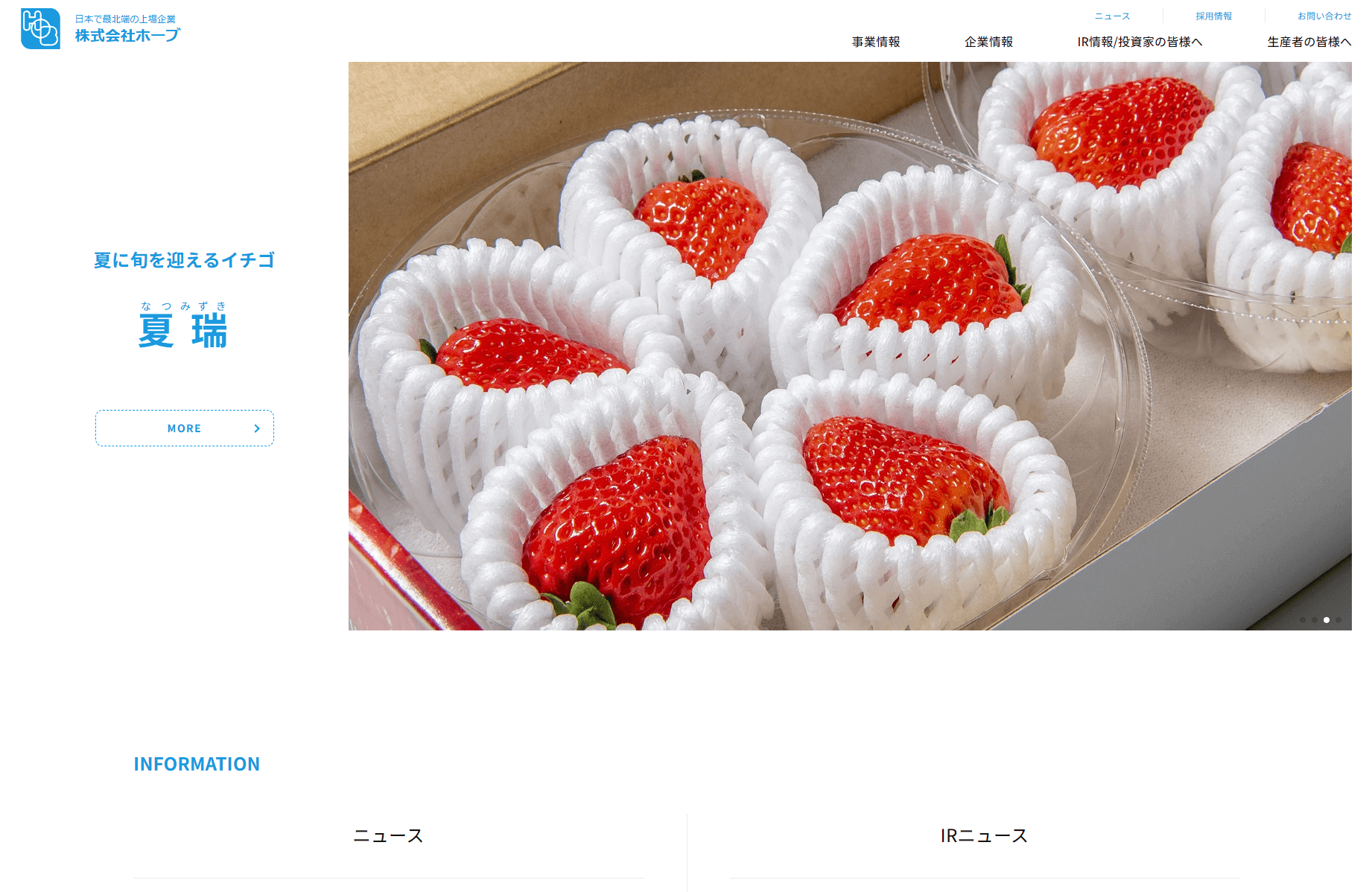
株式会社ホーブ
株式会社WAKU
農業分野の先端技術を活用し、社会課題の解決に取り組む企業です。サステナブルな農業の推進を目指しています。

株式会社WAKU
林業分野の企業
住友林業株式会社
森を資本とみなし、その再生力を未来の技術へ昇華させる企業で、木という素材の可塑性と生命力を読み解き、住まいから都市づくりまで独自の循環思想を編み込んでいます。
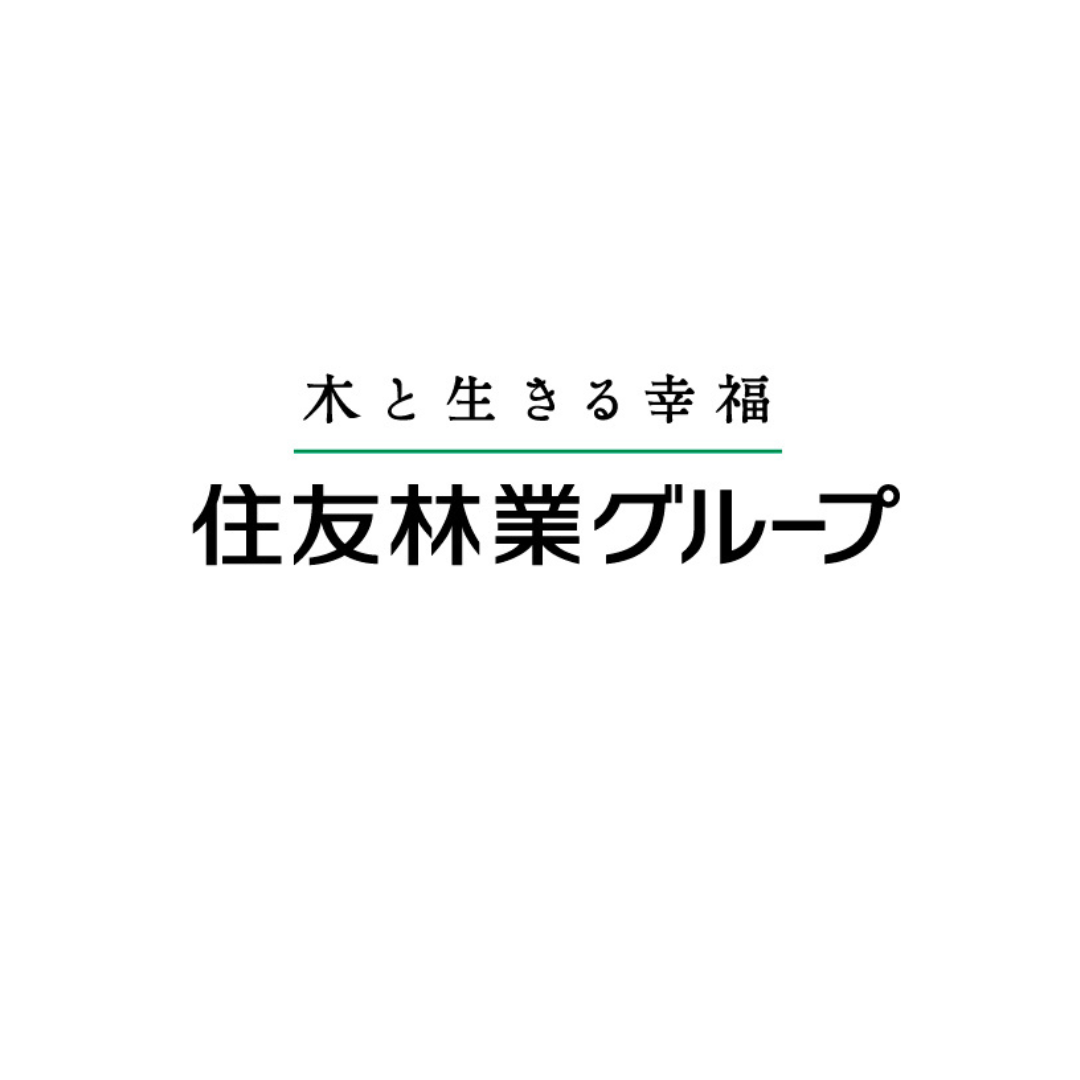
住友林業株式会社
資源環境事業/木材建材事業/海外住宅・不動産事業/住宅・建築事業/生活サービス事業
株式会社柳沢林業
長野県松本市に本社を置く林業会社で、山林の管理やキャンプ場運営、製材加工、薪の販売、農業、日本酒製造など、多岐にわたる事業を展開しています。2021年にはグッドデザイン賞を受賞しています。

株式会社柳沢林業
山林調査、立木の伐採および材木の搬出・加工・販売等
その他の注目企業
オークヴィレッジ株式会社
岐阜県高山市に拠点を持つ企業で、木工製品の製造と森林再生を軸に活動しています。「100年かけて育てた木を100年使う」を理念とし、環境保全型の林業と高品質な木製品の製造を両立しています。

オークヴィレッジ株式会社
木製家具・文具・玩具の製造・販売
木製漆器の製造・販売
木造建築の設計・施工
農業・林業の課題と展望

高齢化と後継者不足
現状
農業・林業ともに担い手の高齢化が進み、後継者不足が深刻な課題になっています。日本国内では、農業従事者の平均年齢が67歳前後、林業では約60歳となっており、このままでは産業を維持できない恐れがあります。業界全体で若年層の参入が求められています。
解決策
若者や異業種からの参入がしやすい環境作りが重要です。農林水産省が行う「新規就農支援事業」では、一定期間、収入補填や技術指導を行い、定着率の向上を図っています。
自然災害への脆弱性
問題点
台風や地震などの自然災害により、農地や山林は甚大な被害を受けます。特に林業では、豪雨による土砂崩れや風倒木が大きな課題で、収益性向上の障壁になっています。
対策
森林環境税の活用により、災害予測技術の向上や防災林の整備が進められています。また、損害保険や共済制度の活用も推奨されています。
サスティナブルな環境保全
背景
地球温暖化の進行に伴い、農業の環境は大きく変化しており、持続可能な農林業への抜本的変質が求められています。過剰伐採による森林破壊や過剰な農薬使用による土壌汚染などが指摘されています。
今後の方向性
持続可能な開発目標(SDGs)を基盤に、環境負荷を減らしつつ、生産性を維持する取り組みが進められています。有機農業や間伐材の有効利用などが事例のひとつです。
農業・林業の将来性

デジタル化の進展
スマート農業と林業
AI、IoT、ドローン、GPS、リモートセンシングなどの先端技術が導入され、データに基づく精密な生産管理が可能になっており、労働負荷の軽減や省力化の実現が目の前にやってきました。病害虫の予測や収穫時期の最適化などはすでに実用化されており、益々の精度向上に期待がかかります。
ロボット技術の活用
GPSやロボットを用いた無人トラクターや収穫機が導入され、大幅な省力化が実現間近です。作業負荷軽減により若者の参入が促されれば、労働力不足が解消されると期待されています。
国内外市場への展開
農林業製品の輸出拡大
日本の高品質な農産物や木材製品の輸出が増加しています。特に、アジア市場において「メイド・イン・ジャパン」ブランドの需要が高まっていますが、中国や韓国による果物などの模倣品も多いため、ライバルとの競争も激化しています。
地元とグローバルの両立
地域特産品を活かした商品開発が進む一方で、航空輸送網の発展もあり、国際市場での競争力強化が図られています。とりわけアジア圏での日本産農作物はブランド化されており、高い人気を維持ています。今後は一層の輸出品目増加が期待されます。
まとめ
農業・林業は、GDPに占める割合や就業者数こそ多くないものの、日本の食料供給と自然環境の維持には不可欠な産業といって差し支えないでしょう。
その特徴は、多様な作物や木材の生産、持続可能な管理方法、技術革新による効率化などが挙げられます。
一方で、高齢化や自然災害などの課題も存在しますが、デジタル技術やグローバル市場への展開が新たな可能性をもたらしています。
少子高齢化に伴い、後継者不足も露呈していますが、新たなテクノロジーや制度改革により、若者の就業や新規参入する企業に期待がかけられています。
農業・林業の未来は、環境保全と技術革新の調和にかかっているといっても過言ではないでしょう。
特に省力化技術によって、地域社会や国際市場でのさらなる競争力の向上が期待されます。
農林水産省
北海道農政事務所
東北農政局
関東農政局
北陸農政局
東海農政局
近畿農政局
中国四国農政局
九州農政局
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター
独立行政法人 家畜改良センター
独立行政法人 農畜産業振興機構
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(本部)
中日本農業研究センター
作物研究部門
果樹茶業研究部門
野菜花き研究部門
畜産研究部門
動物衛生研究部門
農村工学研究部門
食品研究部門
北海道農業研究センター
東北農業研究センター
西日本農業研究センター
九州沖縄農業研究センター
生物系特定産業技術研究支援センター
農業環境研究部門
種苗管理センター
国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター
独立行政法人 国際協力機構
独立行政法人 水資源機構
農林水産技術会議事務局
日本政策金融公庫
一般社団法人 農協流通研究所
特定非営利法人 青果物健康推進協会
公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構
公益社団法人 中央畜産会
一般社団法人 中央酪農会議
公益社団法人 全国食肉学校
一般社団法人 酪農ヘルパー全国協会
一般社団法人 食品需給研究センター
一般社団法人 全国農業改良普及支援協会
公益社団法人 日本農業法人協会
一般社団法人 日本農業機械化協会
一般社団法人 農山漁村文化協会
一般財団法人 農林統計協会
一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構
一般財団法人 肥料経済研究所
一般社団法人 アグリフューチャージャパン(日本農業経営大学校)
公益財団法人 農林水産長期金融協会
畜産情報ネットワーク
全国新規就農相談センター
農業食料工学会
ふるさと回帰支援センター
国際連合食糧農業機関(FAO)
農業協同組合新聞
アグリビジネス投資育成株式会社
JA三井リース株式会社
全国農協青年組織協議会
JA全国女性組織協議会
日本園芸農業協同組合連合会
一般社団法人 全国配合飼料供給安定基金
株式会社JA設計
全国新聞情報農業協同組合連合会
一般社団法人 全国農協観光協会
日本畜産物輸出促進協議会






